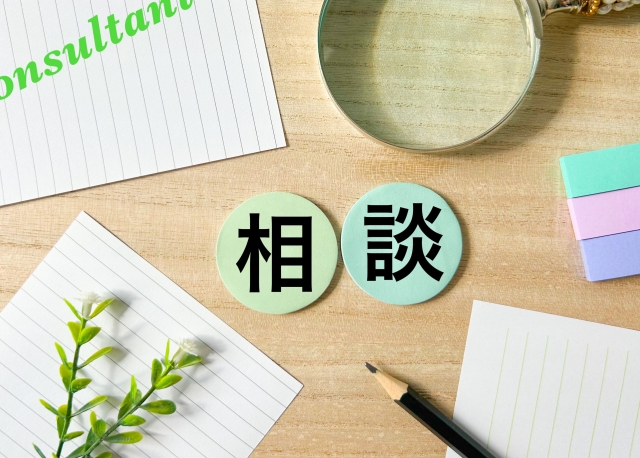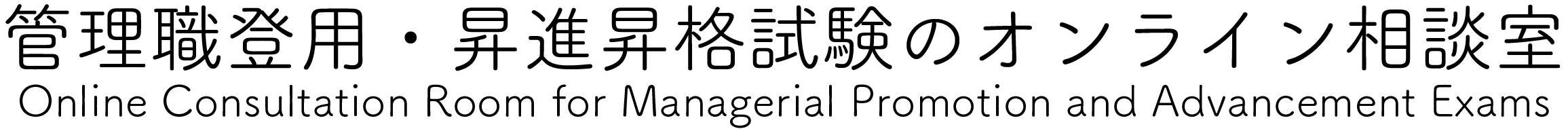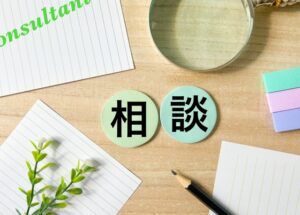はじめに|その「グループ討議」、準備できないと思っていませんか?
人材アセスメント研修におけるグループディスカッション(討議)。
初対面のメンバーと限られた時間で話し合い、しかも評価されるという状況に、「どう臨めばいいかわからない」と不安に感じる方は多いです。
私自身、受検者としても、そして運営側(オブザーバー)としてもこの場に関わってきました。どの受検者も一様に緊張しており、表情はこわばり、空気はピリピリ…。VTR撮影がある場合もあり、その非日常感が緊張をさらに高めます。
この記事では、グループディスカッション演習の本番の雰囲気や、よくある失敗パターン、そして対策のコツについて、私の経験からお伝えします。
グループディスカッションとは?|日常業務の延長にある演習
この演習は、特別なパフォーマンスを求められる場ではありません。課題に対して、メンバーと意見を出し合いながら、より良い結論や方向性を導いていく。まさに日々の仕事の延長線上にある“チームでの問題解決”です。
大切なのは、普段の自分の関わり方。演習形式を知っておくだけでも、心の準備が大きく変わります。
本番の雰囲気|緊張感が高まる
本番の現場は、静かで張り詰めた空気が漂います。
- 最初の演習の場合も多く、参加者はほぼ全員緊張している
- 試験であることを意識して普段のようには振る舞えない
- さらにVTR撮影している場合もあり、過剰に意識してしまう
そして、こんな行動がよく見られます:
- 緊張から必要以上に話しすぎてしまう人
- 逆に黙ってしまって自分を出せない人
普段通りに振る舞うことがいかに難しいか、本番を見ていて実感します。
グループディスカッションの例題
パターン①:役割なし(全員フラット)
例題:
あなたは、ある組織の問題解決の依頼を受けています。今から〇分以内に次の〇ケースについて討議をします。
まず、ケースについて書かれている紙が配られます。短い時間での状況把握が求められます。これも評価項目の一つとなります。
一定時間経過後、討議を始めます。特に明確な役割は事前で決まっていないため全員で場をつくる意識が問われます。また、時間内で複数のケースを取り扱う場合は、時間配分も重要です。
あなたなら、こういった場面でどのような役割を担い、どのような発言をしますか?
パターン②:役割あり(課の代表)
例題:
あなたは製造部〇〇課の課長です。これから、課を代表して来期予算に関する部課長会議に出席します。
来期、〇〇課では△△プロジェクトの推進を予定しており、□□についての予算承認をなんとしても得たい状況です。
このように、役割ありの場合は、例えば課の代表として議論に参加します。
上記の例題のように、ディスカッションの参加する目的としてあなたには達成したいミッションがされています。他方、他の受験者も同じようにそれぞれの役割・ミッションが与えられています。通常、それぞれのミッションは甲乙つけがたく、どれも重要なものです。
このように、グループディスカッション演習では、個人のミッション達成ではなく、グループとしてどう議論を展開し、いかに全体最適な結論を導き出せるかが重要となります。
評価ポイントは?
アセスメントにおけるグループディスカッションでは、「発言の量」ではなく、「どう関わったか」が評価されます。
評価項目は企業によってアレンジされている場合もありますが、基本的には、次の4つの視点が重要です。
傾聴力:相手の話を聴き、意見を引き出す
相手の発言を無表情やリアクションなく聞いていたり、最後まで聞かずに自分の意見を被せてしまうと、「傾聴の姿勢がない」と見なされる可能性があります。
傾聴力とは、相手の意見をうなずきや相づちで受け止めたり、「今のご意見は、○○ということですね」と要約したりすることで、理解しようとする姿勢を示すことができます。その場で「安心して話せる空気」をつくる力とも言えます。
協調性:他者を尊重しつつ、意見交換する
協調性は「相手に合わせる」ことではありません。自分の意見を持ちながらも、相手を否定せずに尊重し、対話を通じてより良い方向性を探ろうとする力です。
例えば、自分とは違う意見が出たときに「それは違う」と相手を否定するのではなく、「なるほど、そういう視点もありますね。そのうえで、私はこう考えています」と建設的に意見することが、協調的な姿勢につながります。
論理性:根拠に基づいた発言ができる
場の雰囲気や感情だけで話すのではなく、「なぜそう考えるのか」という理由や背景を示すことで、発言に説得力が生まれます。
「○○というデータがあるので、私は××が課題だと考えます」「現場では△△という声もあるので、こうした対応が必要かと」など、論理的な構造で意見を述べる姿勢が求められます。
簡潔さも大切ですが、根拠がない発言は浅く見えてしまうので注意が必要です。
リーダーシップ:場全体を整える働きかけができる力
リーダーシップは「たくさん発言すること」や「仕切ること」ではありません。グループ全体が議論しやすくなるように配慮したり、発言が少ないメンバーにさりげなく声をかけたり、話が脱線したときに元に戻したりするような、“場の流れを整える力”が評価されます。
たとえ議論の中心的な存在でなくとも、全体の目的や制限時間を意識しながら進行に貢献しようとする行動が、評価に繋がります。
準備のポイント
私自身の体験から学んだこと
私は受検者として、そして試験運営側として複数回この演習に関わってきました。
私自身が受験した際は、以前別の記事でも書きましたが、1日目のオリエンテーションからとても緊張していて講師の話が頭に入りませんでした。そして、最初の演習であったこのグループディスカッションでは緊張で声が震えたのが自分でもわかりました。
でも、グループディスカッションの途中で気づいたのです。「失敗したくない」「うまくやろう」としすぎて自分らしさを見失いっていたことを。
そこからは「この緊張下でいつもの自分以上の力を見せようとせず、自分らしくやろう」と良い意味で少し開き直ることができました。
また、その後の運営側として参加してわかったのは、「人を見ている」のではなく「関わり方を見ている」ということです。誰でも緊張するようなシチュエーションの中で、そこにどう向き合っているかが問われます。
事前にできる準備と練習方法
グループディスカッションは、日頃の積み重ねが重要だと感じています。本来であれば時間をかけて、自分の議論参加時のクセ(長所・短所)をしっかりと把握し、リーダーとして不足している点は改善を図る努力が必要です。
とは言え、準備期間は短いものの少しでも何か準備をしておきたい!という方もいるかと思います。そういった場合は、演習の型を知るだけでも緊張の軽減に繋がります。
私のサービス(グループ討議・面接対策)では、模擬練習や振り返りも可能です。無料相談も行っておりますので、不安な方はお気軽にお問い合わせください。
📌 グループ討議・面接演習対策オプション概要
- 実際のテーマ例と評価項目のご説明
- 模擬演習
- 模擬演習の振り返りと、今後の課題の共有
まとめ
グループディスカッションで最も大切なのは、あなたらしい関わり方です。目立とうとしすぎる必要も、完璧を目指す必要もありません。
- 遠慮しすぎず、自分の意見を伝える
- 自分の主張を無理に押し通さず、周囲と対話を大切にする
- 普段の業務と同じ感覚で、ほんの少し「前向きなスイッチ」を入れる
本番は緊張しますし、思い通りにいかないこともあります。でも、相手の話に耳を傾け、自分の考えを丁寧に伝えようとする姿勢は、しっかり伝わります。
準備できることを整えたら、あとは落ち着いて、「いつもの自分+α」で臨んでください。
📌以下の記事もあわせてお読みください