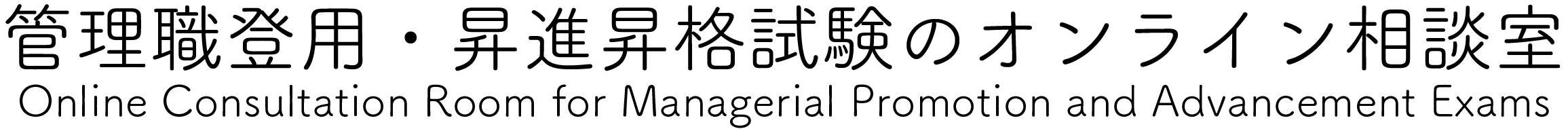はじめに
昇格試験の結果通知を見て、肩を落とした方も多いのではないでしょうか。
面接の手応えがなく、結果も不合格。努力してきただけに気持ちの整理がつかない・・・そんな声をよく聞きます。
でも、昇格試験は一度落ちたら終わりではありません。人事の現場では、初回で不合格になる人が再受験を経て昇格していくケースがたくさんあります。
この記事では、元面接官・現コンサルタントの視点から、「落ちた後にどう立て直せばいいか」「再受験までに何を準備すべきか」を、3つのステップで整理していきます。
昇格試験のよくある悩みと不安の乗り越え方については以下の記事でまとめています。
👉 昇格試験のお悩み相談まとめ
昇格試験に落ちた直後はどうすればいい?
まず大切なのは、結果を受け止めたうえで、冷静に次を考える時間を持つことです。
不合格の結果を見ると、「評価されなかった」「向いていないのでは」と考えてしまいがちですが、人事の立場から見ると、昇格試験の合否は能力だけで決まるものではありません。
昇格枠や昇格率、推薦人数の上限など、個人の努力だけでは左右できない要素が関わるケースも多くあります。
だからこそ、不合格をそのまま「実力不足」と結論づけるのではなく、何が評価され、どこが伝わりきらなかったのかを整理することが重要です。
気持ちの整理がまだ難しい方は、以下の記事も参考になります。
👉 昇格試験が「意味ない・つらい」と感じたときの向き合い方
「不合格=実力不足」と決めつけない
昇格試験の評価は、「試験当日の出来」だけで決まるわけではありません。
面接や論文は、これまでの経験や考え方を限られた時間・情報で伝える場です。そのため、実力があっても、十分に伝わらないまま終わってしまうケースは珍しくありません。
実際、再受験の支援をしていると、最初の対話では良さが見えにくかった方でも、深掘りを重ねるうちに価値観や判断軸が明確になり、「評価される理由」が見えてくることが多くあります。
一方、実際の面接ではそこまで引き出してもらえるとは限りません。不合格の背景には、「能力」ではなく伝え方や整理不足が影響していることも多いのです。
昇格試験がそもそも「何を確認する仕組みなのか」を知っておくと、結果の受け止め方や次の準備の視点も整理しやすくなります。
👉 昇格試験は時代遅れ?それでも企業が試験を行う理由
昇格試験で受からない人に共通する3つの傾向
再受験に向けて立て直す前に、まずは「どこにズレがあったのか」を冷静に見つめ直しましょう。
多くの受験者を見ていると、不合格になる背景には、能力不足というよりも「準備の仕方」や「伝え方」のズレがあるケースが少なくありません。
具体的には、次のような傾向が見られます。
- 準備の偏りがある
論文や面接のどちらかに時間を偏らせてしまい、全体の一貫性が取れていない。 - 評価基準を誤解している
「アピール上手」が評価されると思い込み、組織視点や課題解決力の説明が弱い。 - 本番で力を出し切れない
緊張や想定外の質問に戸惑い、考えてきた内容を十分に伝えられない。
特に三つ目の「本番で力を出し切れない」は、誰にでも起こり得るものです。だからこそ、事前に自分の話し方や構成を整理し、「伝わる形」に整えておくことが重要になります。
なお、「なぜ受からなかったのか」をより具体的に知りたい方は、こちらの記事も参考になります。
👉 【元面接官が語る】昇格面接で受かる人・落ちる人の違いと合否を分けるポイント
再受験に向けた立て直しの3ステップ
では、次の昇格試験に向けてどのように準備を整えればよいのでしょうか。ここでは、再受験に向けた3つのステップを紹介します。
① 振り返る
不合格通知を受け取ったら、上司面談や評価コメントを丁寧に整理しましょう。
「なぜ落ちたのか」を一人で考えるより、評価者の言葉にヒントが隠れています。特に「次回への期待」や「課題」がある場合は必ずメモしておきましょう。
そして、再受験者にとって最も大切なのは「昨年から何が変わったのか」を自分の言葉で説明できるようにすること。
私は面接官時代、再受験の方には必ずこの質問をしていました。
「昨年の受験後、何をどう振り返り、この1年間でどのように成長したのか」。この問いへの答えが明確な人ほど、面接での説得力が大きく変わります。
面接官が見ているのは、前回たとえ不合格であったとしても、そういった困難な状況をどう受け止め、どのように乗り越えたかという姿勢です。その過程にこそ、リーダーとしての人間性や成長意欲が表れます。
② 再設計する
次に、苦手だった領域を中心に、1年単位で計画を立てるのがおすすめです。
- 面接で緊張した → 模擬面接で慣れる
- 論文構成が弱かった → 過去テーマを使って練習する
- 伝える力を高めたい → 上司や同僚にプレゼン機会をもらう
また、日常の業務でも「伝え方を磨く練習」はできます。
打ち合わせや報告の場で、話の組み立てを意識したり、「結論→理由→具体例→再結論」の順で話してみたりすることも立派な実践です。また、社内やお客様への発表、資料説明などを積極的に引き受けるのも良いトレーニングになります。
こうした日々の積み重ねが、再受験時の自信につながります。
③ 継続する
試験対策は短期集中よりも継続力がものを言います。
1年後の再受験直前に慌てて準備を始めるよりも、早い段階から少しずつ継続する方が、結果的に大きな成長につながります。春〜夏にかけては論文、秋は面接準備というように、季節ごとにテーマを分けるのも良い方法です。
そして、第三者の視点を入れることも重要です。
自分では気づかない話し方の癖や弱点、論理の抜けなどを客観的に見てもらうことで改善スピードが上がります。
特に再受験の方は、「昨年と何が変わったのか」「成長した点が伝わる構成になっているか」をチェックすることが欠かせません。
「この話し方、面接官に伝わるかな?」と感じた方は、一人では気づきにくい「話し方のクセ」を一緒に整理していきましょう。当相談室では、実際の回答例をもとにアドバイスしています。
まずは無料カウンセリングからご相談ください。
まとめ
昇格試験の不合格は、キャリアの終わりではありません。一度試験を経験したからこそ、課題や改善点を具体的に捉えられるようになります。
重要なのは、「前回から何が変わったのか」を語れる準備ができているかどうかです。
その視点で1年を積み上げていけば、再受験は十分にチャンスになります。焦らず、着実に立て直していきましょう。
📝 関連記事